トップ画像はにんにく。今年は小さくて個数もそれほどとれませんでしたが、カブは大量にできています。他の野菜たちもぐんぐん成長中。
若い時期に収穫する豆「絹さや」はいろんな調理方法がありますが、我が家ではシンプルに味噌汁にして食べています。


丹波黒大豆などの黒豆は、なぜか祖母が日当たりの悪いところに植えたので生育不良で小さいままです…。元気がなく枯れているものもあったので、水やりを頑張っているのですがあまり期待できませんね。
トマトの生育具合もあまり良くないので、自分で調べたり親戚に相談しているのですが、土壌のpHや植え方など、問題点がたくさんありそうでした。

土壌pHは、本来植える前に確認して調整しておくべきなのですが、今までキチンと計測したことはなかったですし私も本格的に畑のことを勉強してから「いかに大切か」を知りました。
今の時代はネットで調べればなんでも分かる時代ですが、昔はそこまでpHなどは意識されておらず各々の「経験則」だけが頼りになってたので、祖母にpHの事を説明してもあまりピンとこないようです。
開拓史や郷土史、昔の農協関連の冊子を読むと、当時が如何に過酷であったかいうのがよく書かれていますが、土壌研究や改良が進んだのは割と最近になってからの話で、それまでは先祖代々その土地や気候に合わせた農作物が経験則でつくられてきました。
昔とは違い、最近の新規就農者は土壌のことも凄く勉強されている方々が多いようです。
鍼灸治療においても、経験則は大事ですが、今ではEBM(Evidence-Based Medicine=根拠に基づいた医療)が求められる時代ですし、昔よりも色んなことが医学的に解明されています。
経験則も、EBMも大切。そういう点では、神経生理学に基づいた反応点治療は理にかなっていると思います。
土壌改善は、反応点治療でいう《不調の根本を良くする》のと似ているな、と畑仕事をしながらふと思いまいした。
《自然界》と《鍼灸治療》、全く関係ないように思う方もいるでしょうが、畑をすることで共通点や新たな気付きを得ることができます。
~あとがき~
先日のカブの苦味、「調理の時に出汁を大量に入れてしまったから苦かったのでは?」という結論に至りました。
適切な出汁の量で煮るとほとんど苦味がなく、美味しく食べることができました。カブ自体が苦いのかと思って心配していたので、よかったです。
カブは収穫したあとにまた種を蒔くと、どんどんできるので、時期をずらしながら食べることができるのも良いですね。近々、赤カブも植えてみます。

















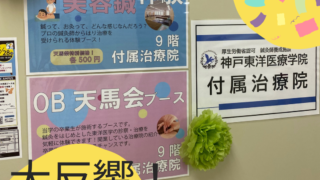



コメント